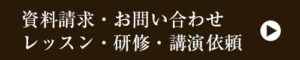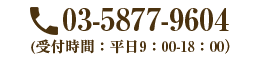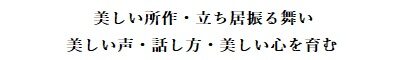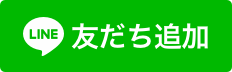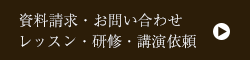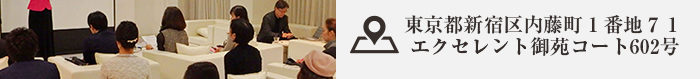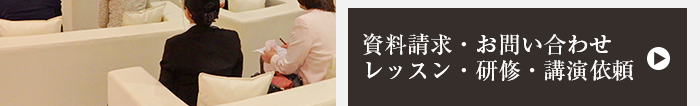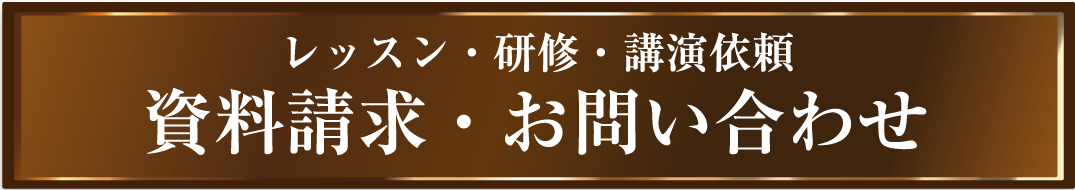2023年9月8日から二十四節気“白露”。9月9日は「重陽の節句」。
由結あゆ美Live2Dモデルが日本の年中行事を解説♪
2023年9月8日から二十四節気“白露”の時期に入りました。
さらに、9月9日は「重陽の節句」。
本日は、この時期の年中行事と開運法について、お伝えします。
★Live2Dは、2Dイラストを立体的に動かすことができる技術です。一般的な3Dモデルとは異なり、2Dイラストをベースにしている為、アニメーションのような手描きの雰囲気を慎重につつ、リアルタイムで表情やポーズを変えることが可能です。
ユウキアユミワールドアカデミーYouTubeでは 「行動に迷いのない最高格のマナーを学び 心身共に整った毎日を生きる」 をテーマにお送りしております。 ぜひ覗いてみてくださいね♪
YouTubeチャンネル登録もお願いいたします✨
ユウキアユミワールドアカデミー
クォンタムヴォイスアカデミー
校長 由結あゆ美