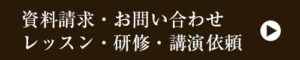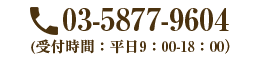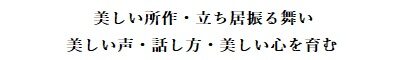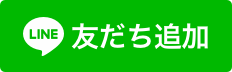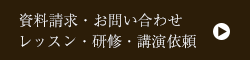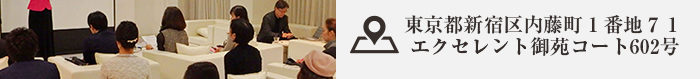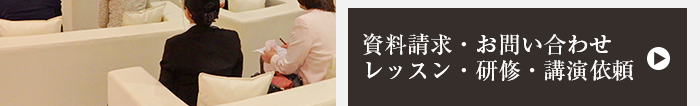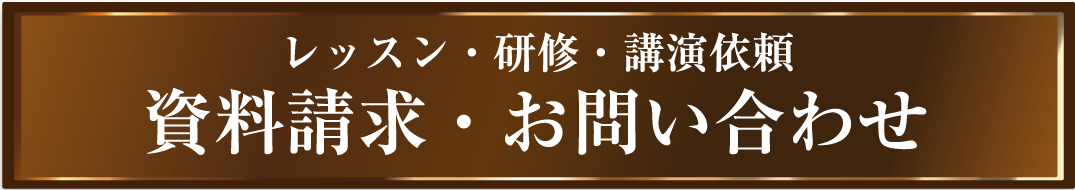“立冬”暦の上では冬が始まりました。
Contents
2022年11月7日から「立冬」に入りました。
二十四節気の一つ。暦の上で冬がはじまる日。太陽の黄経(黄道の一点と春分点とがつくる角度)は225 度。秋分(昼夜の長さがほぼ等しい) と冬至(昼間の時間がもっとも短い)の中間にあたります。
そこで、本日は、この時期に食べておきたい食材と七十二候(二十四節気のそれぞれを初候・次項・末項に分けたもの。一候はおおむね5日間。気候の推移や動植物の変化を表している)について触れていきたいと思います。
冬の季語「大根」にまつわるあれこれ
寒さが増してきて、鍋物が食べたくなる時期に入りましたね。この時期は、寒くなり乾燥してくるため、体は温かさを欲します。根菜類など体を温める食材が多く出回る時期でもあります。
画像元:JAおいらせ
鍋の食材として活躍する大根。鍋物以外にも、芯まで出汁のしみ込んだおでん、真っ白な湯気の立ち上がる風呂吹きや鰤大根。そして、霜の白く降りた朝、短冊に切った大根と油揚げを入れた熱い味噌汁を頂くのもいかにも冬らしい光景です。
また、庭先の大根干し。天日の恵みを受けた大根で調理するとうまみが増し、味に深みが生まれます。さらに、干しあがった大根は沢庵漬けに、切り干しははりはり漬けや煮物となって、冬の食卓を彩ります。
大根はどことなく東洋風の面持ちをしていますが、生まれは地中海東岸。エジプトのピラミッド建設に駆り出された人々には、当時ニンニクと玉葱と大根が支給されたそうです。この古代大根がヨーロッパに伝わってラディッシュとなり、アジアに伝わって大根になったのだとか。さらに、日本では多種多様な品種が生み出されています。
また、台所を彩る大黒さまに大根をお供えする風習が各地に残っています。大根と大国の音が似ているからなのだとか。特に二股の大根を、大黒さまの嫁御と呼んでいるところもあるそうです。
画像元:永田コレクション(島根県立美術館)
『徒然草』には、大根を万病の薬と信じて、長年毎朝、二本ずつ焼いて食べていた人が敵に攻められたときに、大根の化身と名乗る二人の武士に助けられる話があります。兼好法師は、「大根でも深く信じれば功徳があるものだ」と述べています。
冬に活発に動く臓器は“腎臓”
五行論によると、冬に活発に働く臓器は「腎臓」です。
五行論とは、この世界の様々な事項を木・火・土・金・水という5つの要素に還元するという、古くから伝わる東洋的な自然の捉え方です。
五行の考え方の基本の一つに「相生」があります。“木が燃えて火となり、できた灰が土になる。土の中から鉱物が生まれ、鉱物に水が結露し、水が木を育てる”…5つの属性が互いに助け合うように順に影響を与えていくことを表します。季節や体の臓器(五臓)もそれぞれ五行に対応しており、旬の食材を取り入れることで、次の季節に過ごしやすい体を作る準備をすることができます。
補腎作用のある食材「しょうが」
「腎臓」が活発に働く冬。補腎作用のある食材の代表格が“しょうが”です。例えば、「生姜スープ」や「しょうが湯」。生の生姜を基本にした生姜スープは腎臓に補腎作用があります。
ただし、甘すぎる生姜スープは栄養失調の多かった古い時代のレシピなのだとか。砂糖は体を冷やしますし、自然界には濃縮された糖分は存在しないので処理システムが確立されていないため、摂りすぎには注意が必要です。しょうがを意識的に使うことで、腎臓が調子よく働きやすい状態にし、次の季節に備えていきましょう。
二十四節気“立冬”の期間に相当する七十二候
[初候 11月7日~11日頃]
山茶始開(つばき はじめてひらく):サザンカの花が咲きはじめる
水始氷(みず はじめてこおる):水が凍りはじめる
[次候 11月12日~16日頃]
地始凍(ち はじめてこおる):大地が凍りはじめる
地始凍(ち はじめてこおる):大地が凍りはじめる
[末候 11月17日~21日頃]
金盞香(きんせんか さく):スイセンの花が咲き始める
野雞入水為蜃(すずめ たいすいにはいり おおはまぐり となる):キジが海に入ってオオハマグリとなる)
季節の食材や自然界の動植物を意識しながら、改めて周囲を見渡してみましょう。新たな気づきが得られるかもしれません。冬の訪れをじっくりと味わいたいものですね。
ユウキアユミワールドアカデミー
クォンタムヴォイスアカデミー
校長 由結あゆ美